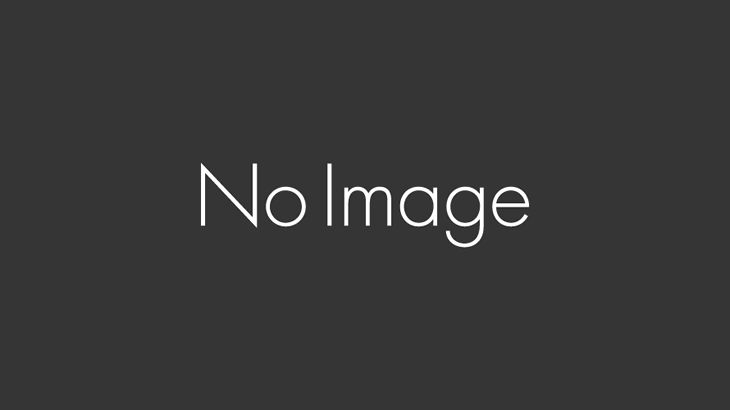カラオケの採点機能で、よく目にする「こぶし」。ビブラートやフォールとちがい、文字からはどのような歌い方なのか分かりにくいため、気になる方も多いことでしょう。
この記事では、こぶしの意味やYouTubeでおすすめの練習動画、こぶしの出し方が綺麗な歌手を6人紹介します。
こぶしのやり方や参考になる歌手を知って練習することで、歌のテクニックを磨いていきましょう。
こぶしとは

こぶしとは、日本に昔から伝わる民謡や、演歌で使われる節回しのテクニックです。同じ母音を伸ばしながら、音程を変えて歌うのが特徴的で、こぶしがあると情感たっぷりに聴こえます。
こぶしという名前から、日本で生まれた歌い方だと思われがちですが、実は海外にも存在しています。過去をさかのぼれば西暦900年ごろ。西洋の教会では「メリスマ」という名前で登場し、時には歌い手を悩ませるほどに、1つの母音にいくつもの音を当てはめて歌われました。また、ゴスペルなどブラックミュージックに起源をもつ音楽では、「フェイク」という愛称で親しまれています。
こぶしは「音程を揺らす」という特徴から、ビブラートと混同されることも多いテクニックです。しかし、ビブラートは一定の間隔で音を上下させるのに対し、こぶしは瞬間的に音を上下させたり、一定の間隔ではない複雑な動きで音程が変わったりします。音程の変化の細かさから「小さい節回し」から「小節(こぶし)」と呼ばれるようになったという説もあるようです。
歌にこぶしを取り入れるためには、横隔膜(おうかくまく)を使った腹式呼吸をする必要があります。その理由は次の2つです。まず、こぶしを使った曲や、こぶしを入れやすい曲はスローテンポのものが多いため、他の曲に比べて肺活量が求められます。また、音程を上下に揺らすビブラートとちがって、複雑な音程の動きに対応するためには、横隔膜に力を入れて音程をコントロールすることが必要です。
そのため、こぶしをマスターしたいのであれば、まずは腹式呼吸を使ってロングトーンを安定させるところから始めましょう。もしそれでもこぶしがやりづらければ、こぶしを入れたい歌詞のところで、実際に拳(こぶし)を握るのもおすすめです。身体全体の余分な力が抜けるため、必要な腹筋の支えだけでこぶしをコントロールできることでしょう。
こぶしがあることで、演歌のように力強さを演出できるのはもちろん、切なさや寂しさ、愛しさなど聴く人の心に訴えかける感情を表現できます。とはいえ、使いすぎるのもナンセンス。正しいやり方や活用方法を知って、歌のレベルをアップさせましょう。
▶まなむすびで「音楽・楽器・歌(ボイトレ)・作曲」を学べる教室情報を探す
こぶしの練習方法

ここでは、YouTubeでこぶしの練習方法を解説した動画を5つ紹介します。初心者の方向けのものから、こぶしに慣れた上級者の方まで、動画の種類は幅広いです。
ぜひご覧いただき、こぶしをマスターする上での参考にしてください。
①こぶしをだすための理論を掴む
「ひょっとこ歌唱研究ch」は、間の抜けたようなひょっとこのイラストが印象的な歌唱研究チャンネルです、
元教員の方が図を交えながら音楽の解説をしているため、感覚的なことよりもまずは理論を掴みたい!という方におすすめします。
中でも、こぶしとビブラートのちがいの図解は、特に分かりやすいですね。
さらに、動画の05:05からは曲のどのような箇所でこぶしを使えるか、実践編もあります。
こぶしの理論を学びたい方から、曲を自分流にアレンジし、こぶしを入れて歌いたい方まで、どの段階の方も参考になる動画です。
②他の歌のテクニックとの違いを踏まえ、基礎練習を行う
山崎裕右(ゆうすけ)さんは、埼玉県で音楽教室を開いているボイストレーナーです。
その歴なんと13年。たくさんの生徒さんを指導した実績を活かして、数々の動画を世に送り出しています。
こちらの動画では、こぶし単体のみならず、しゃくり・フォール・ビブラートと、歌でよく使われるテクニックを解説しています。
こぶしの解説は3:56ごろからご覧いただけます。こぶしの基礎練習としてとても分かりやすいので、ぜひ参考にしてくださいね。
③応用練習!メロディックなこぶしの練習をする
続いて紹介したいのが「アンミュージックサロン」の練習動画。アンミュージックサロンは拠点を大阪におくハリウッド式のボーカルスクールです。スクールが配信している動画というだけあり、練習方法も洗練されており、分かりやすくテンポが良くて参考になります。
動画で解説をしているのは、アメリカのボイストレーニング研究機関IVAの公認ボイストレーナー・Anco.さん。
リズムに合わせて楽しくこぶしの練習ができ、シンプルなこぶしからメロディックなこぶしまで、ステップアップしながら練習できます。「頭を軽く振るとやりやすい」など、具体的な身体の使い方も紹介しているので、初心者の方にもおすすめの動画です。
④実際の楽曲でこぶしを実践してみる
実践を積みながらこぶしの練習をしたい方は、「いくちゃんねる」の動画がおすすめです。
こちらの動画で解説しているいくみさんは、何と現役ボイストレーナー。東京都大田区蒲田にスタジオを構えており、歌が上手くなるための本を出したり、朝日奈央さんや岡田結実さんのレッスンをしていたりと、数々の実績をもっています。
そんないくみさんのこちらの動画では、あいみょんの『空の青さを知る人よ』に注目。ただ聞いているだけでは聞き逃してしまいそうなほど細かなこぶしにフォーカスを当て、スローで歌いながらていねいに解説しています。
実際に『空の青さを知る人よ』を歌いながらこぶしのコツを解説しているので、こぶしのやり方に慣れてきて、曲で実践を積みたい!という方にぴったりです。
⑤プロ演歌歌手によるこぶし講座で、演歌のこぶしのコツを学ぼう!
こちらの金曜ボイスログでは、演歌歌手の松阪ゆうきさんとシンガー・ソング・ライターの臼井ミトンさんと対談する形式で解説しています。こ松阪ゆうきさんは、東京の音楽大学で研鑽を積んだあと、ミュージカル・オペラ・演歌歌手と多方面で活躍しています。
こちらで例として扱っている曲は石川さゆりの『津軽海峡・冬景色』。こぶしの解説はもちろん、演歌ならではのこぶしのやり方についてや、より演歌らしく聞かせるためのコツを、ポイント別に解説しています。
こぶしの中でも、演歌に特化して練習したい!という方におすすめです。
▶まなむすびで「音楽・楽器・歌(ボイトレ)・作曲」を学べる教室情報を探す
こぶしの綺麗な歌手

ここからは、こぶしの綺麗な歌手を男女別に6人紹介します。男性歌手のこぶしで、真似しやすいのは平井堅『瞳をとじて』、リズミカルなこぶしを練習したい方には久保田利伸の『LA・LA・LA LOVE SONG』、さまざまなこぶしを使い分けたい方には青山新の『仕方ないのさ』がぴったりです。女性歌手では、王道のこぶしを聴きたい方には、一青窈の『ハナミズキ』、力強いこぶしなら『夜桜お七』、ハイクオリティなこぶしならAIの『Story』がおすすめです。こぶしを楽しむときの参考にしてくださいね。
こぶしの綺麗な男性歌手
①オーソドックスで真似しやすいこぶし!平井堅『瞳をとじて』
まず、柔らかなウィスパーボイスで人気を博している平井堅。1995年のデビュー後から、『瞳をとじて』や『POP STAR』など、数々のヒット曲を生み出してきました。2020年に活動25周年、2022年に50歳を迎えた現在も、精力的に活動しています。
そんな平井堅のこぶしをたっぷり味わえるのが『瞳をとじて』。
2004年、映画『世界の中心で、愛をさけぶ』の主題歌としてリリースし、100万枚を超えるヒットを生み出した曲です。
中でも2番は、「消えてくのに」「輝いてる」「僕を残して」「過ぎ去ろうとしても」とたくさん登場します。
どれも音程の変化が分かりやすく、真似しやすいこぶしなので、ぜひチャレンジしてみてください。
②アップテンポでリズミカルにこぶしを歌おう!久保田利伸の『LA・LA・LA LOVE SONG』
次に紹介するのは、日本におけるR&Bのパイオニアと呼ばれる久保田利伸。サムライのようなちょんまげヘアとは裏腹に、ブラックミュージックの発声を取り入れた圧倒的な歌唱力で、根強い人気をほこっています。
久保田利伸のこぶしを堪能できるのが『LA・LA・LA LOVE SONG』。木村拓哉と山口智子主演の「ロングバケーション」の主題歌として注目を集めました。
リズミカルな曲調の中に、「でも そのままでいい」「めぐり会えた奇跡が」「涙の色を変えた」とこぶしが散りばめられています。こぶしはバラードで使われることが多いこともあり、歌うときに意識しすぎるとテンポが遅れがちです。リズムキープしたままこぶしを入れる練習をしたい方におすすめします。
③こぶし初心者から上級者まで必見!青山新の『仕方ないのさ』
最後に紹介するのは、今をときめく新進気鋭の演歌歌手、青山新。2020年に19歳でデビューし、若々しく整った顔立ちと、年齢を感じさせない力強い歌声が話題を集めました。
『仕方ないのさ』は青山新のデビュー曲で、演歌らしくたっぷりこぶしが使われています。
歌詞の「仕方ないんだよ」の部分では、初めてでも真似しやすいような音程の変化が大きいこぶしです。一方、「アカシアこみち」の部分ではテクニックが必要な細かなこぶしをきかせています。
さまざまな種類のこぶしを味わえるため、初心者の方はもちろん、こぶし上級者の方も参考にしてくださいね。
こぶしの綺麗な女性歌手
①これぞ王道。こぶし初心者はまずこれを聴いてほしい!一青窈の『ハナミズキ』
まずは、切なさたっぷりの歌声が特徴的な一青窈。2002年のデビューシングル『もらい泣き』がヒットし、日本レコード大賞最優秀新人賞や、NHK紅白歌合戦初出場を決めています。
特に『ハナミズキ』では、「果てないゆめがちゃんと」「続きますように」とたくさんのこぶしが出てきます。
バラード調でゆったりしているため、こぶしも入れやすいので、こぶしビギナーの方はぜひ練習してみてくださいね。
②情緒あふれる力強いこぶしが魅力的!坂本冬美『夜桜お七』
続いて紹介するのは、坂本冬美。演歌・歌謡曲の女王として知られており、ビリー・バンバンのカバー『また君に恋してる』が名を馳せました。
彼女の代表作の中でも、今回注目してほしいのが『夜桜お七』です。1994年に発売され、演歌としては異例のヒットを記録しました。
この曲では、「けとばして」「おなじこと」「はなふぶき」「夜桜おしち」とたくさんのこぶしが登場します。
アップテンポな曲調でありながらも、情感あふれる力強いこぶしは魅力たっぷり。
演歌の魂を受けづぐ、力強いこぶしを堪能してください。
③感情表現と絡めた、ハイクオリティなこぶしを練習したい方はAI『Story』
最後に紹介するのは、日系アメリカ人のシンガーソングライター・AIさん。幼いころから触れてきた本場のゴスペルを取り入れた、パワーあふれる歌い方が特徴的です。
そんなAIの『Story』は、2005年5月18日にリリースされた12枚目のシングル。リリースから約10年後の2014年に公開された映画「ベイマックス」のエンディングテーマを飾るなど、今も根強い人気を誇っています。
『Story』では、曲を盛り上げるためにこぶしを効果的に使っています。1番ではほとんどなかったこぶしが、2番からは曲の盛り上がりに合わせ、“頼ってほしい”“ため息くらい する時もある”“また動き始める”と、2番のサビにかけてたくさん登場。曲全体の抑揚の付け方と、こぶしの使い方を合わせて考えたい方におすすめです。
さらに、AIのこぶしではただ上下に音程が変化するわけではなく、かなり細かく変化します。複雑なこぶしをマスターすることで、あなたのこぶしも一段とレベルアップすることでしょう。